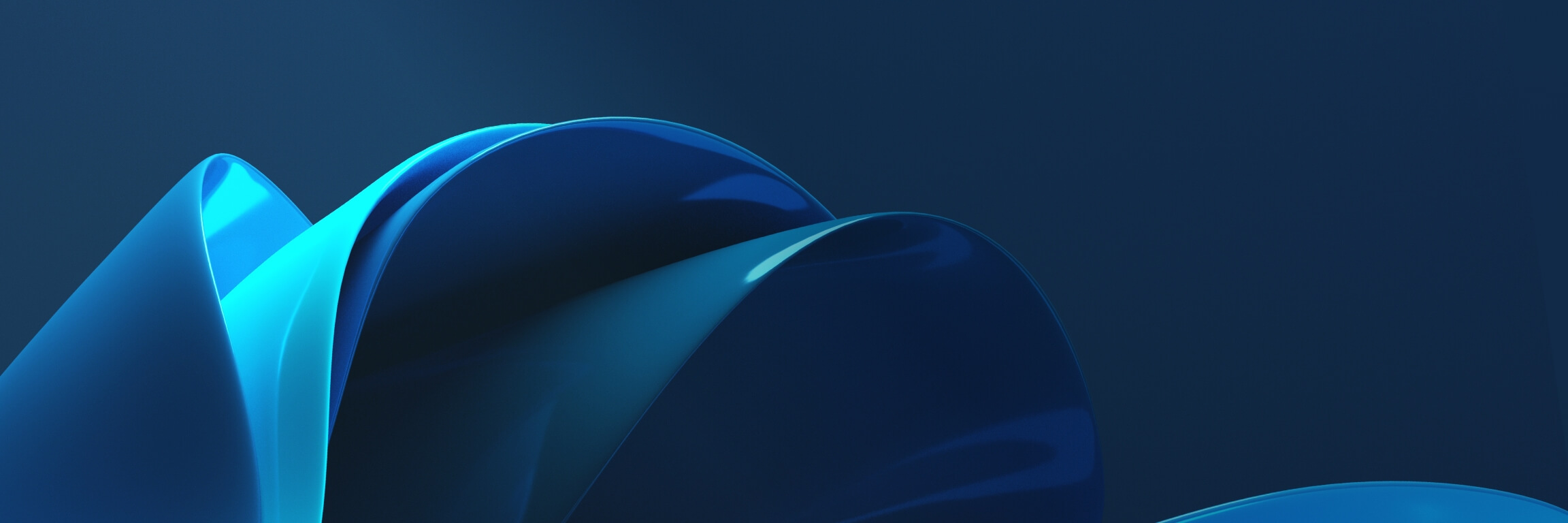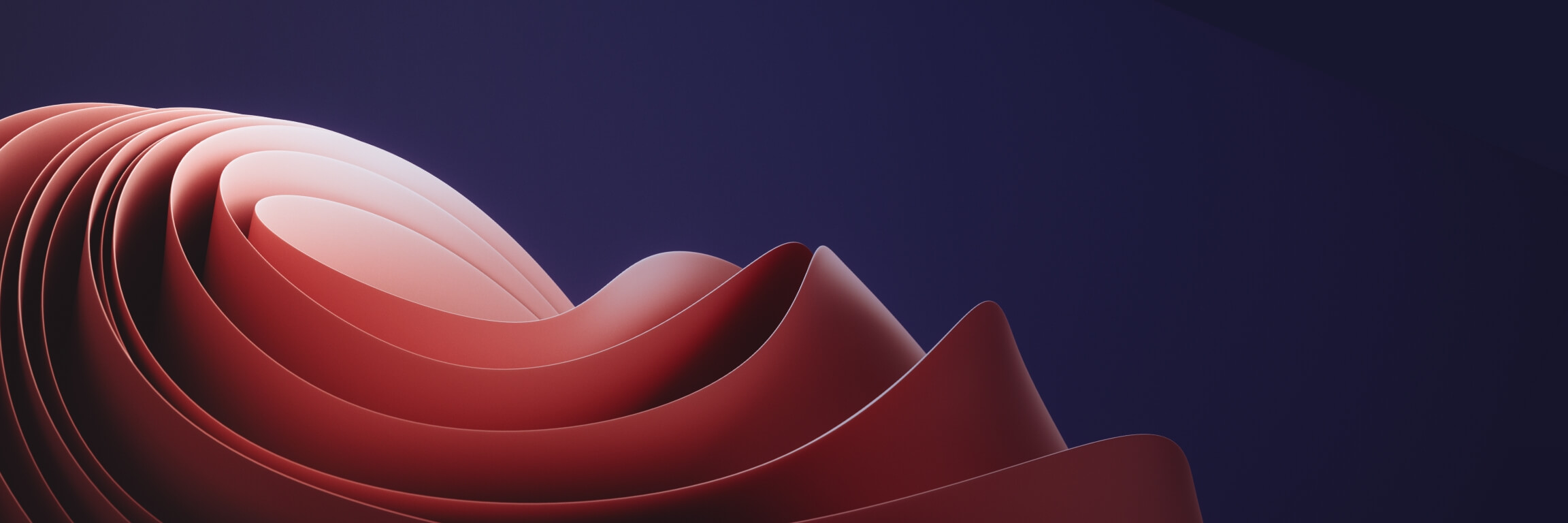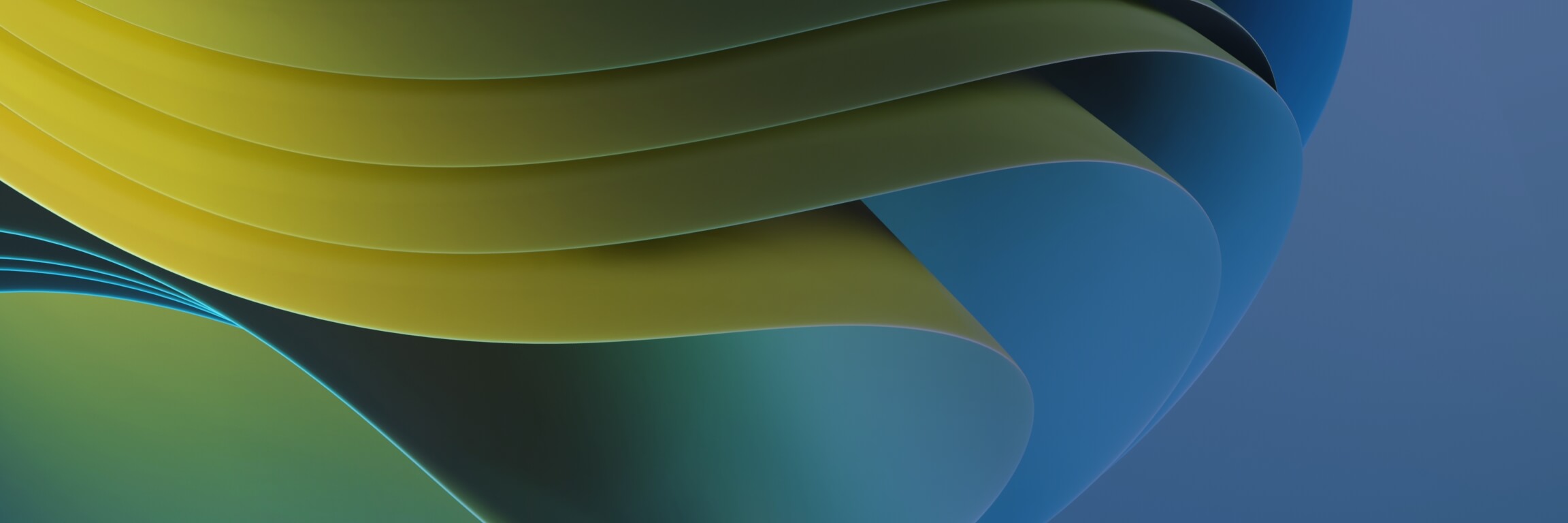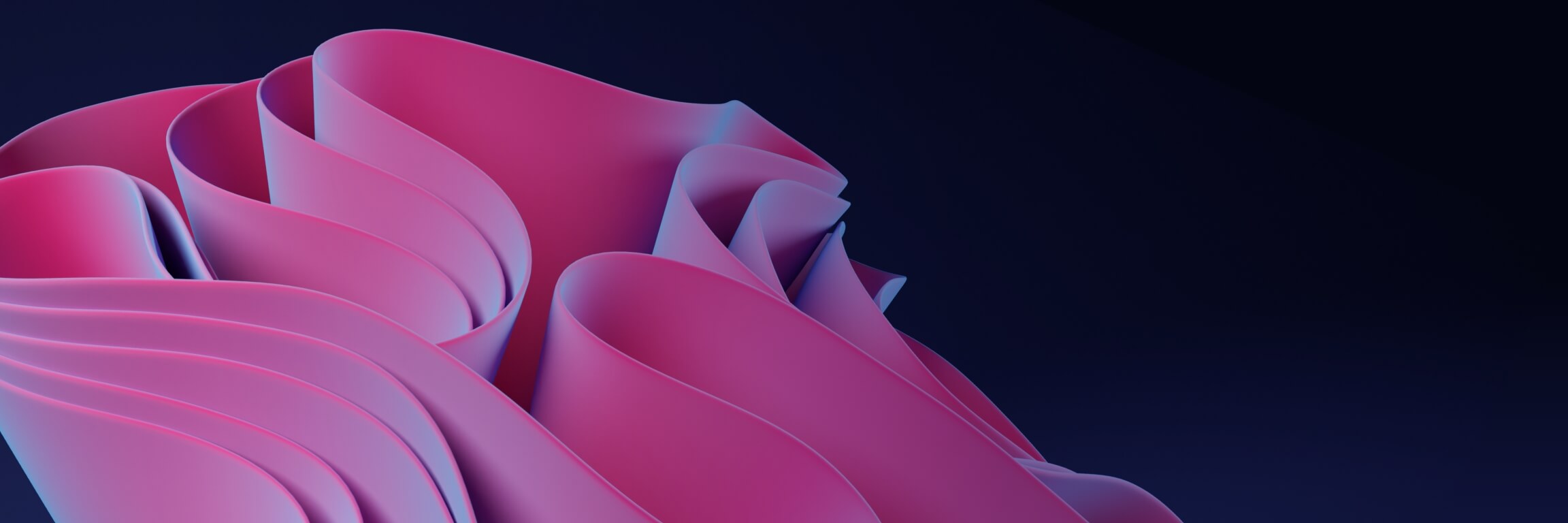従業員福利厚生措置:
当社は2005年1月1日に「従業員福利委員会」を設立し、毎月福利費を計上して定期的に従業員福利活動を実施しています。詳細な福利計画と予算は毎年策定しています。
- 年末賞与および報奨金の支給制度
- 祝日手当および贈答品
- 結婚・弔事・慶弔見舞金制度
- 誕生日手当および記念イベント
- 労働保険・健康保険・団体保険への加入
- 年末パーティーおよび春宴等の社内イベント
- 国内外旅行の補助
- 定期健康診断の実施
退職制度:
当社は「労働基準法」および「労働退職金条例(労使年金制度法)」に基づき、関連する退職制度を実施しています。
労働基準法に基づく退職者の場合:
- 当社は毎月、全従業員の給与総額の2%を退職準備金として積み立て、労働退職準備金監督委員会を設置しています。
- 退職金は勤続年数に応じて計算され、勤続1年につき2基数を支給します。ただし、15年を超える部分は1年につき1基数とし、合計は最高45基数を上限とします。
- 勤続期間が6ヶ月未満の場合は半年として計算し、6ヶ月以上は1年として計算します。
- 業務に起因する身体的または精神的障害によりやむを得ず退職する場合、前項の基準に20%を加算して支給します。
- 退職金計算の基準額(基数計算の基準)は、退職承認時の平均賃金とします。
労働退職金条例(労働年金法)に基づく退職者の場合:
- 当社は、従業員の給与の少なくとも6%を毎月、労働保険局が設立する個人退職勘定(個人年金口座)に拠出します。
- 勤続年数15年以上かつ60歳以上の従業員は、月額退職年金の受給資格があります。勤続年数が15年未満の場合は、一時金として退職金を受け取る必要があります。
- 退職金計算における勤続年数は、実際の年金拠出期間に基づきます。勤務に中断があった場合は、中断前後の拠出期間を合算して計算します。
- 労働年金法施行前に労働基準法の適用を受けていた従業員が、同じ雇用主の下で労働年金法退職制度を選択して引き続き勤務する場合、同法適用前の勤続年数はそのまま保持されます。
労使協定および従業員権利保護措置:
- 定期的な労使会議を開催し、労使協議メカニズムを構築する。
- 従業員苦情処理制度を整備し、労使関係の改善および職場におけるジェンダー平等を推進する。
- 就業規則および人事管理規定を策定し、労使双方の権利・義務および管理事項を明確に定義することで、従業員が自身の権利を十分に理解し、保護できるようにする。
- ホーム
-
キャリア
-
給与と福利厚生